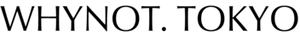珠洲市陶芸センターの共用薪窯を使って実施した共同焼成。
窯元である中堅作家が集い、まだ窯を持っていない若手作家に技術指導を行う貴重な機会となりました。
全4回で構成する若手作家視点での記録レポート。2回目の今回は焼成・前編をお届けします。
【day1】



最初は低温で丸一日かけて、作品や窯じたいの湿気を全体的に抜いていきます。
この時期に薪を使うのはもったいないので製材のときにでる切端(せっぱ)や廃材などを利用しています。
日が落ちて、火を見つめていると 訥々と、でも確かな言葉が、誰からともなくこぼれてきます。
陶芸のことも、日常のことも。誰かとゆっくり話をする機会は、被災後多くはなかったように思います。
【day2】



早朝からイレギュラーが立て続けに発生。
低温の時間帯使おうと思っていた切端が少なく、早い段階で薪に手を付けたこと。
そして薪に手を付けた結果、薪束をまとめたビニール資材をはがしていなかったため
薪が蒸れて湿った状態になっていることに気付いたこと。。


とにかく薪束は天日干ししよう!と、みんなで立てて並べ、
薪の状態を考えると今はやはり切端で焚いておきたい・・・というわけで
薪当番をひとりにお願いし、数名で切端の追加搬入を行いました。
こういう作業を考えると、身体能力以外にもマニュアル免許や中型トラックの運転技術があると便利です。
イレギュラーは発生したけれど、対応できる人数がいる早い段階で気付けてよかったです。
【day3】
中段の薪口を利用した中焚きに入りました。


 薪口前の棚板をはずし、薪で塞ぐように焚いていきます。
薪口前の棚板をはずし、薪で塞ぐように焚いていきます。
薪を投げ込む上焚きまでの、つかの間の休息。
まだ湿り気のある薪は窯のそばに積んで乾かしながらの作業でした。
強還元をかけはじめる温度帯を目安に、中焚きを終了。
中段の薪口はもう使わないのでレンガを詰めて閉じます。

 上焚きの開始です。テンポよく薪を投げ入れていきます。
上焚きの開始です。テンポよく薪を投げ入れていきます。
温度帯1000℃あたりの窯の様子。
窯の近くは冬でも暑いので、タッグを組んで手際よく薪をくべていきます。
薪を多く投じすぎると薪自体の燃焼にばかり熱量を奪われて窯の温度が上がらなくなるので薪が燃えて次の燃料をほしがりそうな頃合いを読む、タイミングが肝要です。
※③焼成・後編につづく