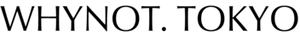珠洲市陶芸センターの共用薪窯を使って実施した共同焼成。
窯元である中堅作家が集い、まだ窯を持っていない若手作家に技術指導を行う貴重な機会となりました。
全4回で構成する若手作家視点での記録レポート。3回目の今回は焼成・後編です。
【day4】

高温帯をキープしたい一日でしたが、湿った薪で温度をあげたり保ったりすることに苦戦したそうです。
(どうりで記録が少なかった…)
薪の天日干しを継続しながら頑張ります。
【day5】



なんとか高温帯を一日乗り切り、最高温度帯でのねらしへ。
現状での色見(焼き締まり具合や灰の乗り具合をみるサンプル)を確認しながら焼成を続けます。
脇では窯を閉じる準備として、モルタルを作っています。

最初の色見確認から二時間後。別の色見を取り出して焼け具合をチェック。
残念ながらこの段階の状態でも手ごたえを感じられず、ダメ押しで焼成を引き延ばしました。
ねらしの時間は十分とれたと判断し、冷却還元と炭化焼成(燻べ焼)を重ねる窯閉じ作業に入ります。
作業に向け、下段薪口前の補助台を撤去し動線を確保します。
下段薪口からロストル下の空間に薪を詰め込み、レンガで閉じます。
続いて、煙道側ダンパーを一旦開放して窯の中の圧力を緩めたら、上段薪口から薪を詰め込みます。
あせってバタバタ投げ入れると、せっかくねらして溶かし流れた灰の上に、新たな灰の粉が降りかかってしまうため
薪は薪口からすべらせるように置いていくのが基本です。
煙道の鉄板を用いて少しずつ煙道を塞ぎ、窯の中の圧力を高めます。
煙や炎が窯の隙間から飛び出してくるほど圧力をかけるのがポイント。
圧力が弱まってきたら、もう一度上段薪口から薪を詰め込みます。
薪を詰め終わったら、薪口は棚板で覆い押さえつけます。
煙道は、鉄板と砂を流し込んで空気の流入をカット。
もくもくと煙がもれ出てくる隙間はモルタルで全て塞ぎます。

これで、ある程度の燃料(薪)が中に蓄えられた状態で、窯が密閉されました。
酸素の供給が遮断された窯の中では、少ない酸素は薪が燃焼し続けるために費やされます。
また、蓄えた薪が燃焼する過程で炭素が発生し、窯の中の作品に吸着されていきます。
陶芸の手法で、部分的かつ意図的に還元焼成を行う場合には、さやに作品と炭を閉じ込めて焼成したりしますが、
それと同じ作業、つまり窯をさやに見立てて、窯全体を還元状態にもっていっているわけです。
須恵器を系譜とした珠洲焼ならではの焼成方法、還元炎燻べ焼。
「数百年前に歴史の途絶えた珠洲焼が現代の知見により再現された」という重みが現在の珠洲焼の基盤であり、
そこから先の、まだ見ぬポテンシャルへとつながっているようにも感じています。
※④窯出し編につづく