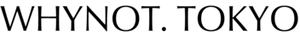珠洲市陶芸センターの共用薪窯を使って実施した共同焼成。
窯元である中堅作家が集い、まだ窯を持っていない若手作家に技術指導を行う貴重な機会となりました。
全4回で構成する若手作家視点での記録レポート。4回目の最後は窯出し編です。

最後に取り出した色味がけして良い状態とは言えず、窯出しの日まで心配し続けた今回のリーダー。
薪の状態が… 還元は効いたか… ねらしの長さは… 灰の溶け具合は…
複数の作家さんが集まると、失敗は自分事では済まない。
焼成した作品の行先、展示販売の予定、納品のデッドライン。。
慣れない窯でのイレギュラーな共同焼成。肩にかかる重みは別次元だったと思います。



窯を閉じた翌朝には窯の温度は357℃まで下がっていたので
窯の中に残る薪をきれいに燃やし尽くすため、下段薪口をすかして空気を通しました。
そうして迎えた窯出しの日。
みんなが集合した時点でもまだ窯の温度が作業できるほどには下がっていなかったため
中段薪口や煙道の砂を取り除いて空気を通し、さらに冷ましていきます。
(いきなり空気が入りすぎないようブロックを除去した後の薪口は板でざっくり覆うなどしています。)

ブロックをはずし始めたときに思わず中を確認。
大丈夫、ちゃんと黒くなっているよ!
リーダーが安堵し、顔色が一気に明るくなった瞬間でもありました。


窯が冷めるまでの合間に、使った場所をみんなで清掃。
次に使う人が気持ちよく使えるようにするのも共用窯を利用する上での大切なポイントです。
そして、窯出し前の少し早めの腹ごしらえ。こういう何気ない時間のおしゃべりもとても良かったです。
窯を閉じてから窯出しの日を迎えるまでの間、どれだけ不安だったかを振り返り吐露するリーダー。
たしかに、窯を閉じるタイミングを判断するときにこの状態の色味が出てくると、
かなり迷いが生じるし、窯出し当日まで不安しかなかったかもしれません。
いざ、窯出し。一番手前、火前に置いた物たちが次々と出てきます。
うまく焼けてほしかったものは概ね取れている様子。本当に良かった。
その人なりの目玉作品が良い焼きで出てくると、都度場がなごみます。
窯の中に置いていたオルトンコーン(熱量がどこまで高まったかを傾きで確認する焼成小道具)も
しっかり倒れていたようです。つまり、焼き不足の心配もあまりなさそうということ。
棚板などを取り払って、奥へ奥へと進んでいきます。



窯の中はまだ蒸し暑く、選手交代。
作品を密に詰めて衝立のようにし、熱が抜けるのを防ぐ作戦…蓄熱の功労者ともいえる花入れ達。
おかげでどの作品も良い色に仕上がっています。



中堅作家、それぞれに手ごたえのある作品が出来上がりました。
珠洲焼らしい、素朴で、でも存在感のある焼き上がり。
自分達それぞれの窯でないことは残念ですが、復旧半ばのこの時期に作家が集い
中堅から若手へ、様々な指導を受けながら作品を焼き上げられたことは
珠洲焼という伝統工芸を細々とでもつないでいく、確かな一歩だと感じました。

*** END ***