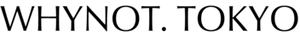珠洲市陶芸センターの共用薪窯を使って、本プロジェクト2回目の共同焼成が実施されました。
今回は、5月に中堅作家から技術指導を受けた若手作家4名が主体となり、準備から焼成までの一連の工程を実践。
焼成準備の段階では地元珠洲に残るリーダーが、震災後少なくなった薪の取扱業者を探して燃料を調達したり、窯に詰める作品量や若手の経験値の不足を補うためにベテラン作家に声をかけて協力を仰ぐなど、決められたスケジュールで事業を完遂するために奔走してくれました。
21日午前9時。窯詰めをスタートし、その夜から火入れ。


若手作家たちは、5月に技術指導を行った中堅作家に要所要所で確認をしながら、ひとつ、またひとつと判断を重ねて慎重に焼成を進めました。
というのも、焚き手が変わると焼成への持論やアプローチ方法が微妙に異なっていたそうで。

結果として「今、この窯の中ではどんな炎を必要としているか」「窯の状態をどのように持っていきたいか」ということに都度着目して知見を得ながら薪をくべたそうです。
予定では窯閉じの作業を25日朝からとしていたところ、24日深夜から日が変わる頃には早くも火前の焼きが仕上がってきたため、火の勢いを押さえて粘りつつ、窯閉じが早まっても問題のないよう集う時間を早め、いつでも臨戦態勢に。
午前2時、窯の中腹あたりの色味を確認すると程よい具合。
作品にのった灰を溶かしきるのに必要な時間を考えると、これ以上の引き延ばしは火前の作品が焼け過ぎる…。
その決断のもと、1時間後の午前3時に火前の色味を引き出した上で窯閉じ作業を開始、午前4時に焼成を終了する形となりました。
窯の正面では短時間で薪をたくさん詰めて薪口を閉じ、窯の後方では煙道を鉄板と砂で塞ぎ炎を窯に閉じ込める。
どちらの作業も体力勝負なので女性ばかりの若手作家たちにとっては正に最後の試練だったと思います。
29日午前9時。しっかり温度管理がなされ、定刻での窯出し。

閉ざされた窯を封切すると、自然釉がしっかりのった独特の黒い肌の精悍な作品たちが佇んでいました。


想定よりも早い時間で焼成が終了していたことや、焚き手によるアプローチの違い、杉と松の薪を併用したことによる影響など、5月の共同焼成のときとはまた違ったイレギュラーの数々でしたが、ベテラン勢の知見を糧に若手作家たちは見事に乗り越えてくれました。



全ての作品が取り出されてようやく「歩留まりが気になるが、音(焼き締まり)はそれなりに良いように思う。焼き色は安心した。本当に学びの多い焼成だった。」と話した若手リーダー。
人の作品の出来を預かる共同焼成。
その場を纏めるプレッシャーをしっかり感じていたようです。
手際よく清掃作業も終わり、各々作品の確認をしながら手入れを行い。
秋晴れの夕日が照らす中、素晴らしい実りと収穫で第二回共同焼成を終えることができました。